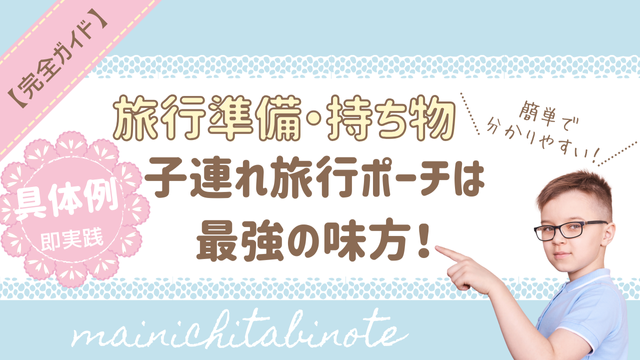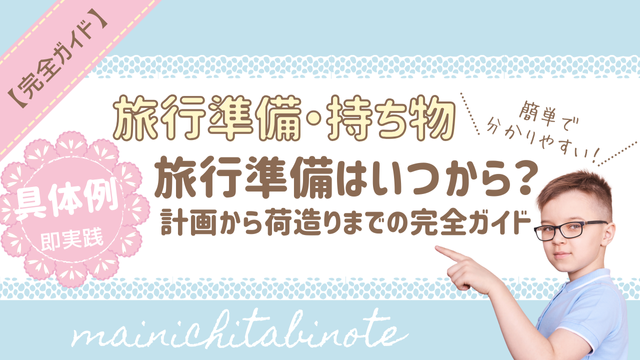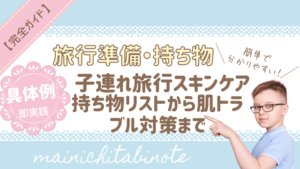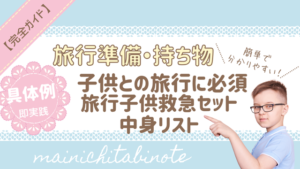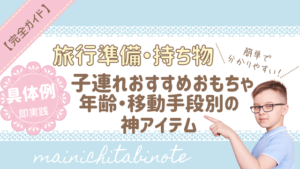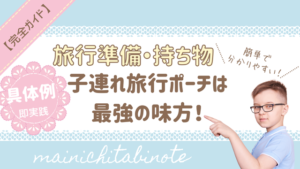旅行の準備って、旅行準備はいつから始めたらいいか、本当に悩みますよね。特に国内旅行のパッキングはいつから手をつけるか、旅行準備の荷造りはいつからが正解か分からなかったり、旅行の計画は何日前から立てるべきか迷ったり…。
子連れだと持ち物もどんどん増えますし、小学生や赤ちゃんがいるご家庭だと、持ち物の完全版リストが欲しくなっちゃいますよね。「子連れ旅行だけど荷物は少なくしたいのに!」なんて心の叫び、すごくよく分かります。そ
れに、旅行に行くなら何ヶ月前が安くていいですか?なんてお得情報も気になるし、そもそも旅行は何ヶ月前から決めるのがベストなんでしょう?
そんなあなたの尽きない悩みをまるっと解決して、スマートな旅の達人になれちゃう方法を、この記事でたっぷりお伝えしますね!
- 旅行の計画から荷造りまでの最適なタイミングがわかる
- 忘れ物がなくなるシーン別の持ち物リストを作れる
- 大変な子連れ旅行の荷物をぐっと減らすコツがわかる
- お得に旅行するための予約時期の知識が身につく
みんなの旅行準備はいつから?計画編

旅行は何ヶ月前から決めるのが良い?
「よし、旅行に行こう!」と思い立ったら、まず気になるのが「で、いつから動き出せばいいの?」ってことですよね。結論から言うと、旅行の種類や目的によって最適な時期は変わりますが、一般的には2〜3ヶ月前から動き出すのがおすすめです。
例えば、飛行機や新幹線を使う旅行の場合、多くの交通機関では早期割引、いわゆる「早割」が設定されています。これを狙うなら、2ヶ月以上前からの予約が断然おトクになります。人気の観光地や特定のイベントが目的の場合も、ホテルの予約がすぐに埋まってしまうため、早めの行動が肝心です。
私の大失敗談なんですけど…
友達と「沖縄行きたいねー!」なんて話が盛り上がって、出発の1ヶ月前に予約しようとしたら、航空券もホテルもびっくりするくらい高くて!結局、予算オーバーで旅行先を変更した苦い経験があります(涙)。人気のシーズンは、本当に早い者勝ちなんですよね。
一方で、デメリットもあります。あまりに早く決めすぎると、急な仕事や体調不良で予定が変更になるリスクも考えられます。キャンセル料がかかる場合もあるので、予約する際にはキャンセルポリシーをしっかり確認することが大切ですよ。
予約時期のポイント
早めの予約(3ヶ月以上前)がおすすめなケース
・ゴールデンウィークやお盆、年末年始などの繁忙期
・航空券や新幹線の「早割」を利用したい場合
・絶対に泊まりたい人気のホテルや旅館がある場合
じっくり検討(1〜2ヶ月前)で良いケース
・平日など、比較的空いている時期の旅行
・行き先を特に決めていない、気軽なぶらり旅
このように、自分の旅行スタイルに合わせて「いつから決めるか」を判断するのが、賢い旅の第一歩です。
旅行に行くなら何ヶ月前が安いの?

せっかくの旅行、どうせなら少しでもおトクに行きたいのが本音ですよね!旅行が安くなる時期は、主に「交通機関のセール時期」と「旅行先のオフシーズン」を狙うのがセオリーです。
まず、航空会社は年に数回、大規模なタイムセールを実施します。LCC(格安航空会社)はもちろん、大手航空会社でも半額近くになることがあるので、見逃せません。これらのセールは、搭乗日の数ヶ月前に開催されることが多いです。旅行会社のパッケージツアーも、「早割プラン」として3ヶ月前くらいからお得な料金を提示し始めます。
セールで激安チケットをゲットした成功体験!
航空会社のメールマガジンに登録しておいたら、ある日「72時間限定タイムセール」のお知らせが!ちょうど行きたかった北海道へのチケットが、往復で1万円以下だったんです!即決して、最高の旅行ができました。情報収集って大事ですね!
また、旅行先の「オフシーズン」を狙うのも賢い方法です。例えば、沖縄なら梅雨明け直後や台風シーズンを避けた秋口、北海道なら雪まつり前後を避けた春先などが比較的安くなる傾向にあります。一般的に、大型連休明けの平日や、1月下旬〜2月、6月、11月あたりは旅行費用が下がりやすいと言われています。
実際に、旅行費用は時期によって大きく変動することが公的なデータからも分かります。
データで見る旅行費用
総務省統計局の家計調査報告を見ると、長期休暇のある月(例えば8月など)は、他の月に比べて旅行関連の支出、特に宿泊料や交通費が大きく増加する傾向が見られます。これは、需要が高まることで価格が上昇するためです。
参考情報サイト: 総務省統計局「家計調査報告」
URL: https://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/index.html
これらの情報から、旅行を決めるのは安さを追求するなら3ヶ月〜半年前。セール情報にアンテナを張りつつ、オフシーズンを狙って計画を立てるのがおすすめです。
旅行の計画は何日前から立てるべきか
予約が完了したら、次は具体的な旅行計画ですね!これも旅の醍醐味の一つですが、一体いつから手をつければいいのでしょうか。私の経験上、旅行の計画は「ざっくり」と「きっちり」の2段階で進めるのがおすすめです。
1ヶ月前~2週間前:ざっくり計画フェーズ
この時期は、旅の骨格を決めるときです。「絶対に行きたい場所」「絶対に食べたいもの」を3つくらいリストアップします。そして、それらの場所の位置関係を地図アプリなどで確認し、大まかな行動ルートをイメージします。この段階では、時間を分刻みで決める必要は全くありません。「1日目はAエリア、2日目はBエリア」くらいで十分です。
計画魔だった私の失敗談…
初めての京都旅行で、15分刻みの完璧なスケジュールを立てたんです。でも、いざ現地に行くと、バスが渋滞で遅れたり、思ったよりお土産屋さんが楽しくて長居しちゃったり…。計画通りに進まないことにイライラして、全然楽しめなかったんです。それ以来、計画は「余白」が大事だと学びました。
1週間前~3日前:きっちり計画フェーズ
出発が近づいてきたら、少しだけ計画を具体的にします。行きたいお店の営業時間や定休日をチェックしたり、移動手段(電車、バス、タクシー)の時間や料金を調べておくと安心です。特に、本数の少ないローカル線やバスを利用する場合は、事前の確認が必須ですよ。
以下に、計画のステップを簡単な表にまとめてみました。
| タイミング | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 1ヶ月前 | 行きたい場所・食べたいものをリストアップ | 優先順位をつけて3〜5個に絞るのがコツ |
| 2週間前 | エリア分けと大まかなルート決め | 地図を見ながら「1日目はここら辺」と決める |
| 1週間前 | 営業時間・交通手段の確認 | 「行ったら休みだった…」を防ぐ! |
| 3日前 | 最終確認・予約が必要なものは手配 | 人気のレストランなどは予約しておくとスムーズ |
完璧な計画を目指すのではなく、「旅のしおり」を作るような楽しい気持ちで進めるのが、計画倒れしないコツです。
最初に作るべき旅行の準備リスト
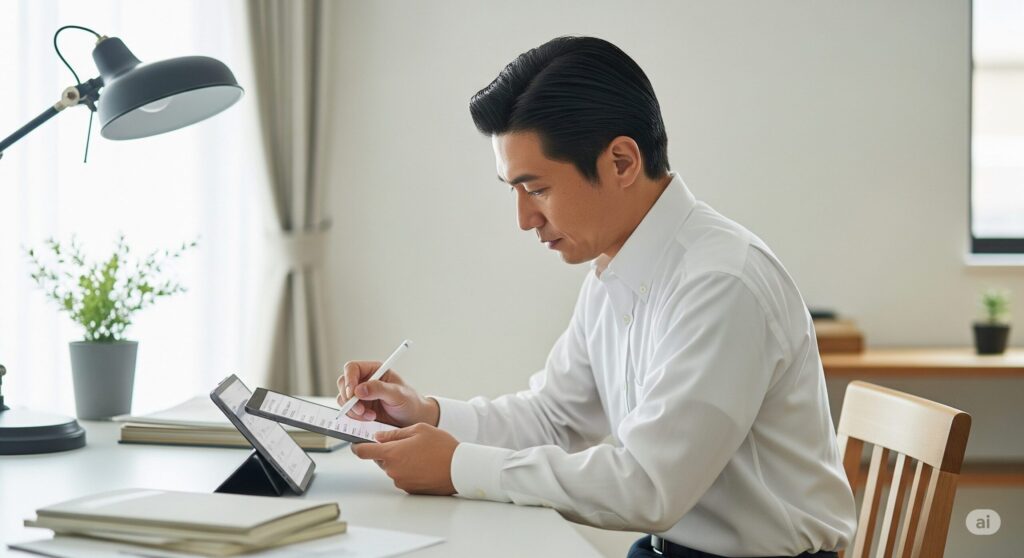
旅行準備をスムーズに進める最強の味方、それが「準備リスト」です!これがあるだけで、頭の中が整理されて、忘れ物を劇的に減らすことができます。私がいつも作っているリストのカテゴリをご紹介しますね。
マイ準備リストの作り方
- 持ち物リスト:衣類、洗面用具、ガジェット類など、カバンに入れるもの全て。
- やることリスト(To-Do):航空券の予約、ホテルの予約、旅行保険の加入、仕事を休む連絡など。
- 買うものリスト:旅行用に新しく必要なもの(日焼け止め、常備薬、旅行サイズのシャンプーなど)。
- 調べることリスト:現地の天気、交通情報、行きたいお店の口コミなど。
これらをスマートフォンのメモアプリや、手帳に書き出しておくだけでOK。終わった項目からチェックを入れていけば、進捗が一目で分かって安心感が違います。
特に「持ち物リスト」は一度作ってしまえば、次の旅行でも使い回しができます。旅行のタイプ(国内、海外、出張、レジャーなど)別にテンプレートを保存しておくと、さらに便利になりますよ。
リストのおかげで助かった経験!
海外旅行のとき、「やることリスト」に「海外旅行保険の加入」と書いていたのをすっかり忘れていて…。出発3日前にリストを見返して、慌てて加入しました。もしリストがなかったら、保険なしで行くところでした。本当にリスト様様です!
準備を始める一番最初にこのリストを作ることが、効率的な旅行準備への一番の近道です。
子連れ旅行の荷物を少なくするコツ
「子連れ旅行は荷物が多くて当たり前」…なんて、諦めていませんか?いくつかのコツさえ掴めば、驚くほど荷物をコンパクトにできるんです!
現地調達&レンタルを活用する
おむつやかさばるお菓子、ベビーフードなどは、全てを持参せず、旅先のドラッグストアやスーパーで調達すると決めてしまうのがおすすめです。最近は、ベビーカーやベビーベッドをレンタルできる宿泊施設も増えています。予約時に確認してみましょう。
衣類は「着回し」と「圧縮」がカギ
子供の服は汚れやすいので多めに持っていきがちですが、基本は「日数分+1セット」で十分。ボトムスは着回しのきくシンプルなものを1〜2本に絞り、トップスで変化をつけましょう。そして、最強の味方が圧縮袋です。驚くほど衣類がかさばらなくなるので、100円ショップなどでぜひ手に入れてください。
荷物パンパンだった私の過去…
初めての子連れ旅行では、「あれも必要かも」「これもなかったら不安」と、巨大なスーツケースがパンパンに!でも、結局半分くらいは使わなかったんです(笑)。次の旅行からは「最悪、現地で買えばいいや」と割り切ったら、荷物が半分以下になって、移動がすごく楽になりました。
おもちゃは厳選する
移動中やホテルで子供を飽きさせないためのおもちゃは必須ですが、これも厳選が大事。軽くてかさばらないシールブックや、お絵かきセット、小さなぬいぐるみなど、お気に入りを2〜3個に絞りましょう。スマートフォンのアプリや動画配信サービスに頼るのも一つの手です。
荷物を減らす魔法の言葉
荷造り中に迷ったら、「これは本当に必要?代用できない?現地で買えない?」と自問自答してみてください。この一手間で、不要な荷物がどんどん減っていきますよ。
旅行準備はいつから?荷造り・持ち物編

国内旅行のパッキングはいつからが多数派?
旅行準備のクライマックスとも言えるパッキング(荷造り)。これ、いつから始めるか、本当に人それぞれで面白いですよね!インプットした情報を分析すると、大きく3つのタイプに分かれるようです。
| タイプ | パッキング開始時期 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| じっくり準備派 | 1週間~1ヶ月前 | ・忘れ物に気づきやすい ・買い足す時間が十分ある ・心に余裕が生まれる | ・普段使うものを詰めてしまい不便 ・旅行気分が長すぎて疲れることも |
| 標準派 | 2~3日前 | ・旅行の実感が湧いて楽しい ・必要なものを冷静に判断できる ・バランスが良く、最も多いタイプ | ・急な買い出しが必要になることも ・仕事が忙しいと焦る可能性がある |
| 直前スパート派 | 前日~当日 | ・荷物が最小限になる ・パッキングの時間が短い ・旅慣れている感が出る(笑) | ・忘れ物をするリスクが最も高い ・当日の朝はバタバタしがち |
調査によると、男性は「1ヶ月以上前」から準備する人が最も多く、女性は「1週間くらい前」が最多、次いで「前日」という結果も出ています。面白いですよね。
私は典型的な「標準派」です!
2日くらい前にスーツケースを広げて、ポイポイと必要なものを投げ込んでいきます。そして前日の夜に、最終チェックをしながらきれいに詰めるのがマイルール。これが一番、忘れ物もなく、直前のワクワク感も味わえて気に入っています。
どのタイプが正解というわけではありません。自分の性格や旅のスタイルに合ったタイミングを見つけることが、ストレスのないパッキングの秘訣です。
旅慣れた人の旅行準備、荷造りはいつから?

旅慣れた人、いわゆる「旅の達人」たちは、荷造りに関しても自分なりの哲学を持っています。彼らの共通点は、「準備は早く、荷物は少なく」です。
彼らの多くは、旅行が決まった段階で、前述したような「持ち物リスト」を更新し始めます。そして、実際のパッキングは前日か当日の朝に、リストを見ながら短時間で済ませてしまうことが多いようです。
なぜそんな短時間でできるのか?その秘密は「パッキングの仕組み化」にあります。
達人が実践するパッキング術
- カテゴリ別ポーチ収納:下着、スキンケア、ガジェット類など、カテゴリ別にポーチを分けて収納。スーツケースの中がごちゃつかず、取り出しもスムーズです。
- 衣類は立てて収納:衣類を丸めたり畳んだりして、ファイルボックスに書類を立てるように収納します。これにより、何がどこにあるか一目瞭然になり、下のものを取り出すために上を崩す…なんてことがなくなります。
- アメニティは旅行用を常備:シャンプーや歯ブラシなど、普段使っているものとは別に、旅行用のセットを常に用意しています。これにより、出発当日の朝に「あ、歯ブラシ詰めるの忘れた!」と慌てることがありません。
私の友人で、年間30回以上出張に行く「出張のプロ」がいるのですが、彼の荷造りは見ていて惚れ惚れしますよ。スーツケースを開けたら、まるでパズルのようにポーチがピッタリ収まっていて、必要なものをサッと取り出すんです。準備にかかる時間は、なんとたったの15分だとか!
旅慣れた人の準備は、まさに「段取り八分、仕事二分」。事前のリスト作りと仕組み化こそが、スマートな荷造りを実現するんですね。
基本的な旅行準備の持ち物チェック
ここでは、「これさえあれば、とりあえず何とかなる!」という基本的な持ち物をチェックリスト形式でご紹介します。パッキングの最終確認にぜひ使ってくださいね。
【絶対必須】これがないと始まらない!
- 現金・クレジットカード:キャッシュレス化が進んでも、現金が必要な場面は意外と多いです。
- スマートフォン・充電器:地図、連絡、写真…今や旅の生命線。モバイルバッテリーもあると最強です。
- 交通機関のチケット類:航空券や新幹線の切符。eチケットの場合は、すぐに表示できるように準備。
- 身分証明書・健康保険証:運転免許証やマイナンバーカード、そして万が一のケガや病気に備えて保険証は必ず携帯しましょう。
- 家の鍵:意外と忘れがち!帰ってきたときに家に入れなかったら悲しいですからね。
薬を忘れないで!
普段から飲んでいる常備薬がある方は、絶対に忘れないでください。日数分+予備を忘れずに。また、飲み慣れた胃腸薬や頭痛薬、酔い止めなども持っていくと、急な体調不良の際に安心です。
【身だしなみ】快適に過ごすために
- 着替え・下着・靴下:日数分+1セットあると、汚れたり濡れたりしても安心。
- 化粧品・洗面用具:普段使っているものを小分けボトルに移し替えるとコンパクトになります。
- コンタクトレンズ・眼鏡:視力が悪い方は必須ですね。ワンデータイプのコンタクトは予備を多めに。
- ハンカチ・ティッシュ:エチケットの基本です。ウェットティッシュもあると何かと便利。
これらの基本の持ち物さえ押さえておけば、大きなトラブルなく旅行を楽しむことができますよ。
あると安心な旅行の持ち物【子連れ編】

前述の基本の持ち物に加え、子連れ旅行では、子供の年齢に応じた特別なアイテムが必要になります。ここでは、年齢を問わず、多くのファミリーに共通して「あってよかった!」と言われる持ち物をピックアップします。
子連れ旅行の三種の神器
- おしりふき:おむつを卒業した子でも、手や口を拭いたり、テーブルの汚れを拭いたりと大活躍!除菌タイプがおすすめです。
- 大きめのビニール袋やジップロック:汚れた服を入れたり、ゴミ袋にしたり、濡れた水着を入れたり…と用途は無限大。数枚カバンに忍ばせておくと、必ず役立ちます。
- 子供用の常備薬・ケア用品:子供用の解熱剤、絆創膏、虫除け、日焼け止めなど。普段から使い慣れているものを持っていくのが安心です。特に体温計は必須アイテムですよ。
ビニール袋に救われた話。
サービスエリアで子供がジュースを盛大にこぼして、全身びしょ濡れに!着替えはあっても、濡れた服を入れるものがなくて困っていたとき、カバンの奥から出てきたビニール袋が神様に見えました(笑)。それ以来、大小さまざまな袋を持ち歩いています。
また、子供が好きなお菓子や飲み物を少し持っていくと、移動中のぐずり対策になります。食べ慣れない現地の食事を嫌がったときの「保険」にもなりますね。
年齢別!小学生のいる子連れ旅行の持ち物
子供が小学生になると、自分のことができるようになる一方で、新たなニーズも生まれてきます。低学年と高学年に分けて、あると便利な持ち物を見ていきましょう。
低学年(1~3年生)向けの持ち物
この時期は、まだまだ親のサポートが必要ですが、「自分専用」のものが嬉しいお年頃。子供用の小さなリュックに、自分の荷物を少しだけ持たせてあげると、責任感が芽生えて喜ぶかもしれません。
- 暇つぶしグッズ:音の出ないお絵かきセット、迷路や間違い探しの本、折り紙などがおすすめです。長時間の移動も楽しく乗り切れます。
- お気に入りのタオルや小さなぬいぐるみ:環境の変化で不安になったとき、慣れ親しんだものがあると安心します。
- 歩きやすい靴:観光でたくさん歩くことを想定し、履き慣れたスニーカーを用意しましょう。新品の靴は靴擦れの原因になります。
リュックを持たせたときの失敗談…
息子が喜ぶと思ってお菓子やおもちゃをパンパンに詰めたリュックを持たせたら、出発して30分で「パパ、重いから持ってー」と(笑)。結局、大人の荷物が増える結果に。子供に持たせる荷物は、本当に軽くて最低限のものだけにするのが教訓です。
高学年(4~6年生)向けの持ち物
自分でできることが増え、少し大人びてくる高学年。本人の希望も聞きながら準備を進めると、旅行への主体性が高まります。
- 子供用カメラやスマートフォン:旅の思い出を自分の視点で記録させてあげるのは、とても良い経験になります。
- 読書用の本や電子書籍:本好きな子なら、移動時間や夜のホテルでの読書タイムも楽しめます。
- お小遣いと財布:自分で予算を管理しながらお土産を選ぶ練習にもなりますね。
年齢に合わせて持ち物を工夫することで、子供にとっても親にとっても、より快適で思い出深い旅行になりますよ。
赤ちゃん連れ安心!旅行の持ち物完全版

赤ちゃんと一緒の旅行は、楽しみな反面、準備が一番大変かもしれません。でも、ポイントさえ押さえれば大丈夫!「これさえあれば安心」という持ち物をまとめました。
YMYL情報に関する注意
以下の情報は一般的な持ち物リストですが、ミルクやベビーフードなどの成分やアレルギー情報については、必ず公式サイトをご確認ください。赤ちゃんの健康に関わることなので、断定的な情報は避け、あくまで参考としてご活用ください。
【食事・ミルク関連】
- 粉ミルク・哺乳瓶:日数分より少し多めに。スティックタイプの粉ミルクや、使い捨ての哺乳瓶が荷物を減らせて便利です。
- 液体ミルク:お湯がなくてもすぐに飲ませられる液体ミルクは、移動中や外出先で大活躍します。(参照:各乳業メーカー公式サイト)
- ベビーフード:普段食べ慣れているものを数食分。
- 授乳ケープ:母乳育児の場合、どこでも安心して授乳できます。
- マグやストローマグ:水分補給に。
【おむつ・衛生関連】
- おむつ・おしりふき:かさばりますが、1日分はすぐに取り出せるマザーズバッグに入れておき、残りはスーツケースへ。現地調達も視野に入れましょう。
- おむつ用消臭袋:使用済みおむつを入れるエチケット。
- 着替え一式:最低でも2〜3セットは手荷物に入れておくと、急な吐き戻しやおむつ漏れに対応できます。
- ガーゼ・スタイ(よだれかけ):何枚あっても困りません。
【その他】
- 抱っこ紐・ベビーカー:移動手段やシーンによって使い分け。
- 保険証・母子手帳:急な体調不良に備えて必ずセットで。
- お気に入りのおもちゃ:ぐずり対策の最終兵器。
最近は、ベビー用品のレンタルサービスも充実しています。ベビーソープや保湿剤なども用意してくれるホテルもあるので、事前に問い合わせてみると、荷物をぐっと減らせますよ。
自分に合った旅行準備がいつからか考えよう
- 旅行準備を始める最適なタイミングは旅行の目的やスタイルによって変わる
- お得に旅行するなら予約は2〜3ヶ月前、オフシーズンやセール時期を狙うのがおすすめ
- 旅行の計画は1ヶ月前から「ざっくり」始め、出発が近づいたら「きっちり」詰めるのがコツ
- 最初に「持ち物」「やること」「買うもの」の準備リストを作ると忘れ物が激減する
- 子連れ旅行の荷物は現地調達やレンタルサービス、圧縮袋の活用で少なくできる
- パッキングを始める時期は「じっくり派」「標準派」「直前派」など人それぞれ
- 自分に合ったタイミングを見つけることがストレスのない準備につながる
- 旅慣れた人は事前のリスト作りと準備の仕組み化で、短時間でパッキングを終える
- 基本的な持ち物は「絶対必須」と「身だしなみ」に分けてチェックすると確実
- 子連れ旅行ではおしりふきやビニール袋、子供用のケア用品が三種の神器となる
- 小学生の荷物は「自分専用」を意識し、年齢に合った暇つぶしグッズを用意する
- 赤ちゃんの荷物は液体ミルクや使い捨て哺乳瓶などを活用するとコンパクトになる
- 宿泊施設やベビー用品のレンタルサービスを事前に調べておくのも重要
- 完璧を目指しすぎず、旅のプロセスを楽しむ気持ちが大切
- 最終的には「自分に合った準備の始め方」を見つけることが最高の旅につながる